
伊勢神宮に行ってきました。
ついに念願の伊勢神宮へ行ってきました。「お伊勢さん」と呼ばれるだけあって、日本人なら一度は行ってみたい聖地。行ってみたら「えっ!2カ所ある」「えっ!知らなかった」家に帰ってから旅を振り返りながら伊勢神宮について調べてみました。
写真は、参拝した時の写真を使用しています。
伊勢神宮は2カ所ある。
伊勢神宮は、正式には「神宮」といいます。神宮は「内宮(皇大神宮)」と「外宮(豊受大神宮)」があり14所の別宮、43所の摂社、24所の末社、42所の所管社があります。これら125の宮社全てをふくめて神宮といいます。
内宮には皇室の御祖先の神と仰ぎ、私たち国民の大御祖神として崇敬を集める「天照大御神(あまてらすおおみかみ)」、外宮には衣食住を始め産業の守り神である「豊受大御神(とようけのおおみかみ)」が祀られてます。

伊勢神宮は、内宮と外宮があるの知らなかったよ。神宮は125の宮者全てを神宮と言うんだね。
参拝は外宮から内宮の順で参拝をします。
式年遷宮とは?

「式年遷宮」は、20年ごとに御正殿・諸殿舎・御装束神宝をすべて新しくして、大御神様に新宮へお遷りいただき、国と国民の平安と発展を祈るお祭りです。天武天皇のご発意により、持統天皇4年(690年)に第1回が行われました。1300年にわたって受け継がれています。
次回の式年遷宮の最も重要な儀式「遷御の儀」は、令和15年の秋となります。しかし、関連したお祭りは、令和7年よりすでに始まっています。

長い時間をかけてお祭りをするんだね。
外宮(豊受大神宮)参拝

ご祭神の豊受大神宮は、天照大御神の食事を司る女神。名前の豊は豊かさを表し、受は食べ物を表しています。内宮のご鎮座から約500年後、第21代雄略天皇が夢に現れた天照大御神の神託に従い、丹波の国から豊受大御神を招きました。以来、豊受大御神は食事を司る「御饌の神」として伊勢神宮の外宮にご鎮座しています。

五丈殿・九丈殿は、雨天時の祭典でのお祓いや遙祀を行うための建物です。

三ツ石は、3個の石を重ねた石積みです。この前で、御装束神宝や奉仕員を祓い清める式年遷宮の川原大祓が行われます。

次は、内宮に行ってみよう!
内宮(皇大神宮)参拝

御祭神の天照大御神は、皇室の御先祖で八百万の神々の中心に位置し、太陽にも例えられる神様。約2000年前、天照大御神の鎮座地を探して各地を巡っていた倭姫命が、天照大御神のお告げにより五十鈴川のほとりに内宮を建てたのが伊勢神宮の起源といわれています。
宇治橋

宇治橋は、内宮に入るための大事な架け橋。大鳥居と宇治橋を見るとこれから聖域に入るのだなと心が引き締まります。宇治橋は、全長101.8ⅿ、幅8.4ⅿ、床板や欄干は「檜」で橋脚は「欅」でできています。
宇治橋は、明治22年(1889年)の式年遷宮から遷宮にあわせて20年に1度、架け替えられることになりました。20年に1度架け替えられるのは、遷宮の4年前が恒例となっています。
宇治橋にある大鳥居は、内側・外側共に7.44ⅿあります。
五十鈴川


五十鈴川は、別名「御裳濯側」と呼ばれています。倭姫命が御裳のすそを濯いだことから名付けられたと伝えられています。御手洗場では、手水舎と同じようにお清めができます。
御厩

皇室から献上されている神馬がいる場所。毎月1日、11日、21日の8時くらいに正宮にお参りをします。

はじめての伊勢神宮。知らないことばかりでしたが、神聖な領域はとても美しく、清らかな空気と静寂に心が洗われる思いでした。日常を離れ、心が整う時間を過ごせました。
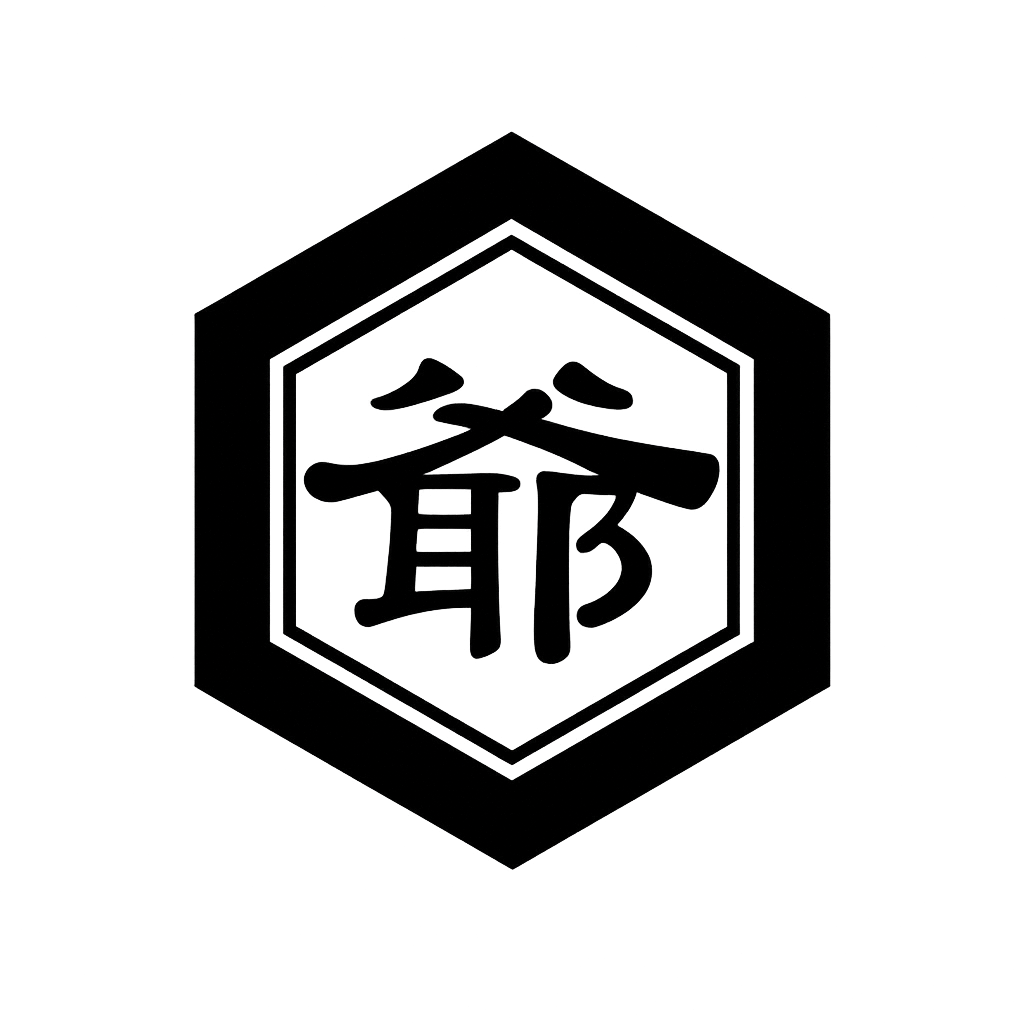

コメント